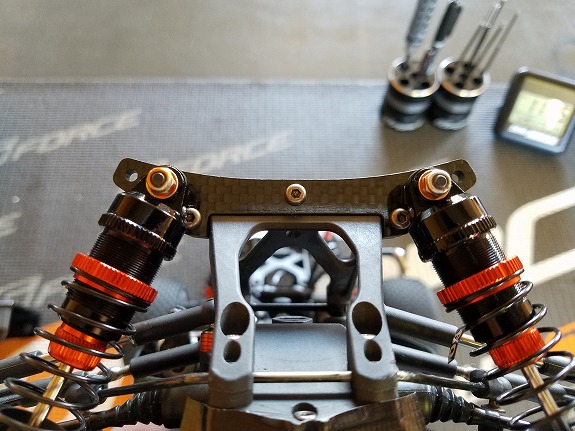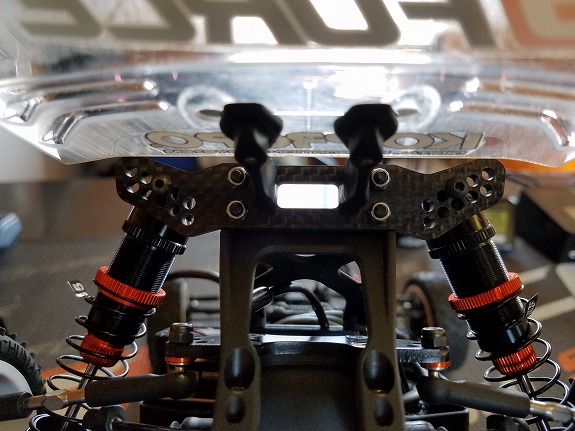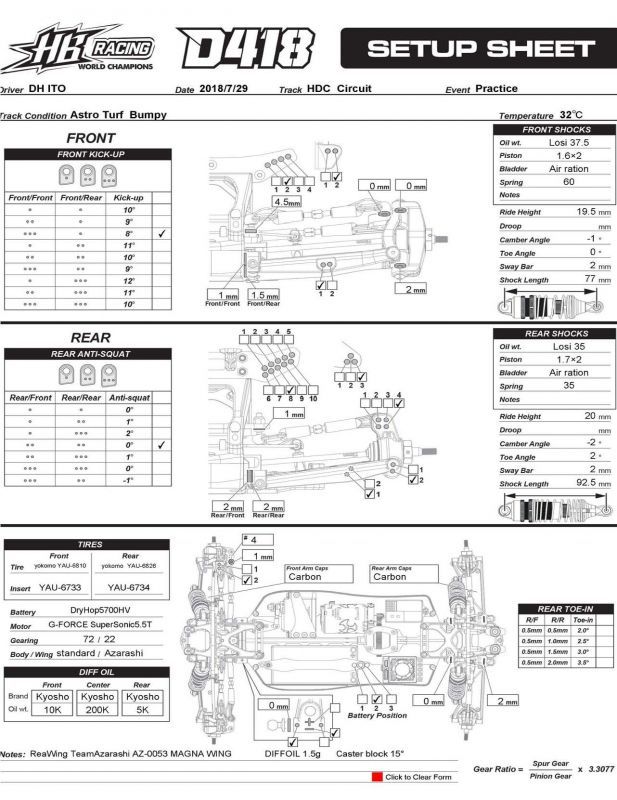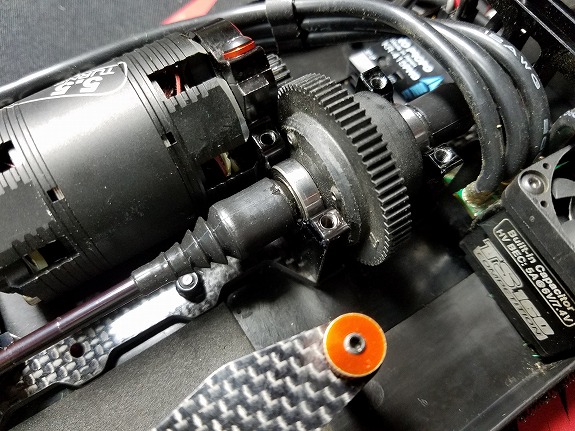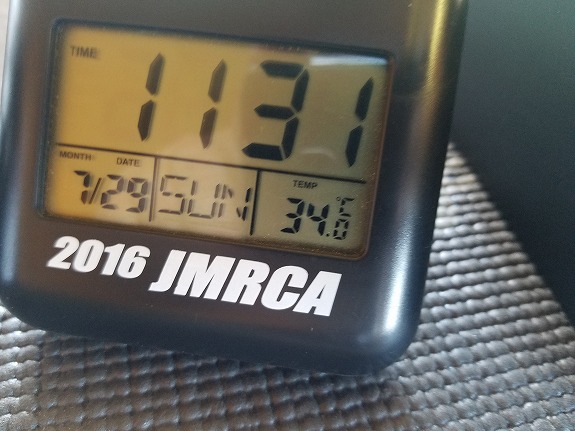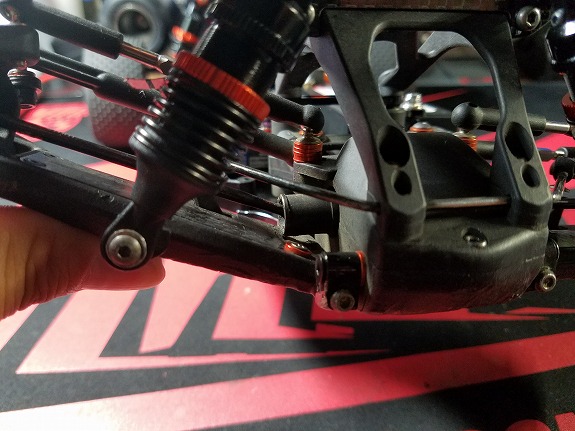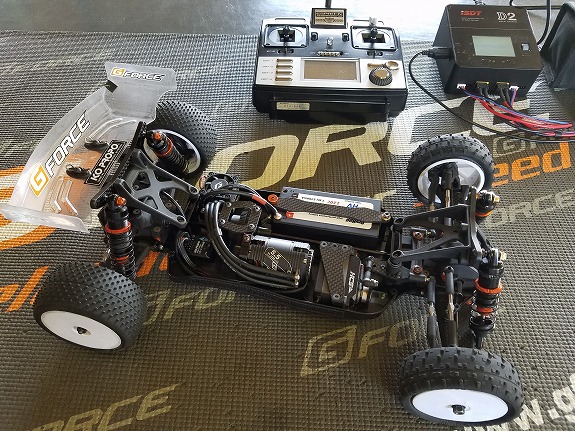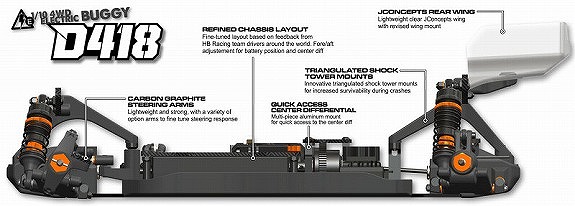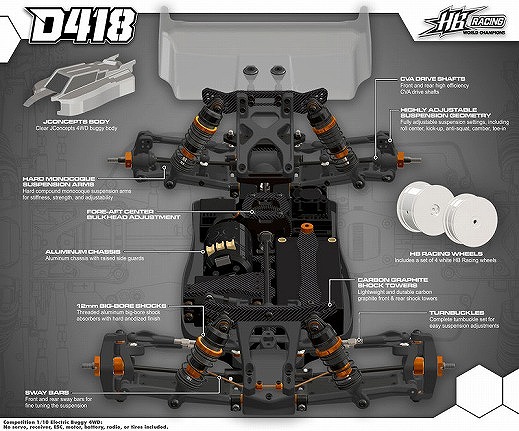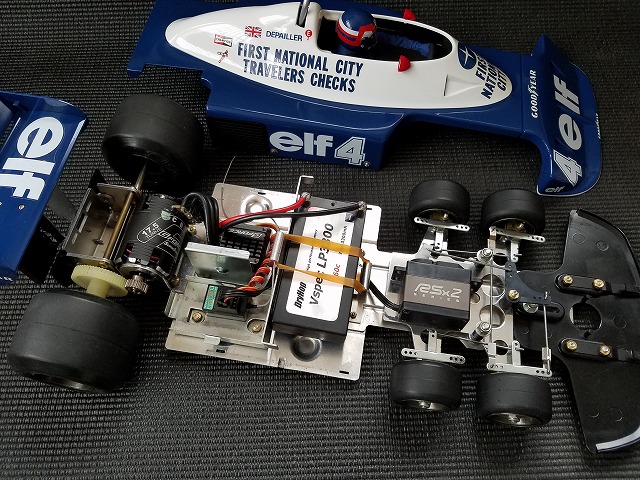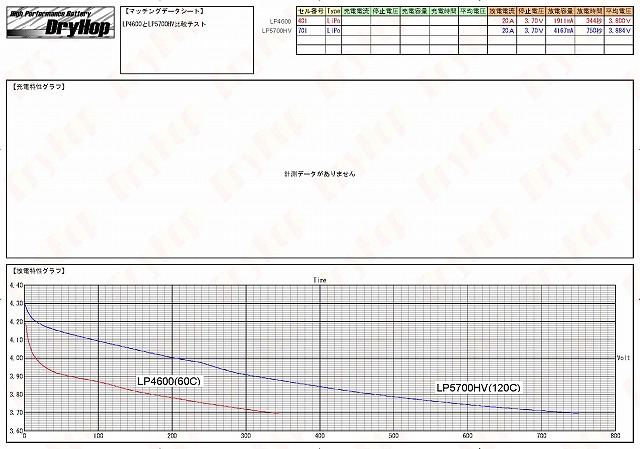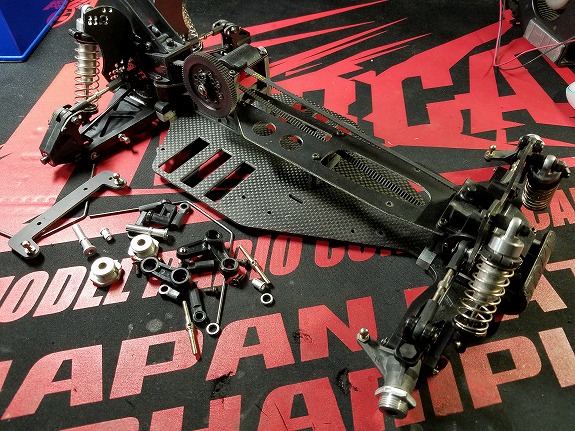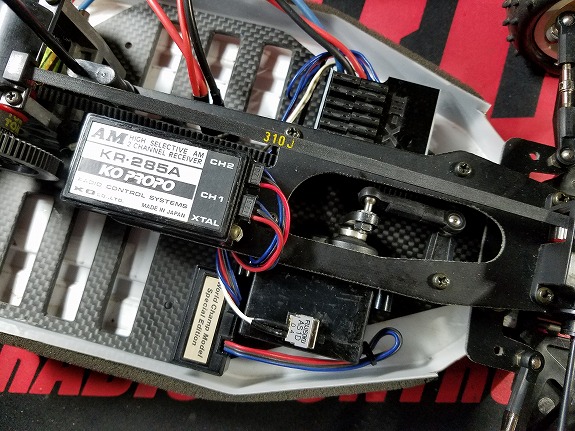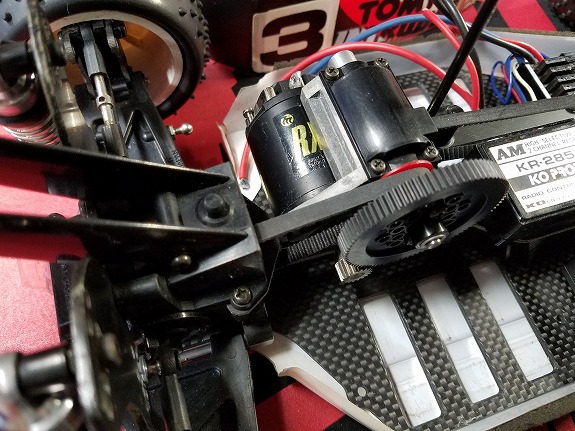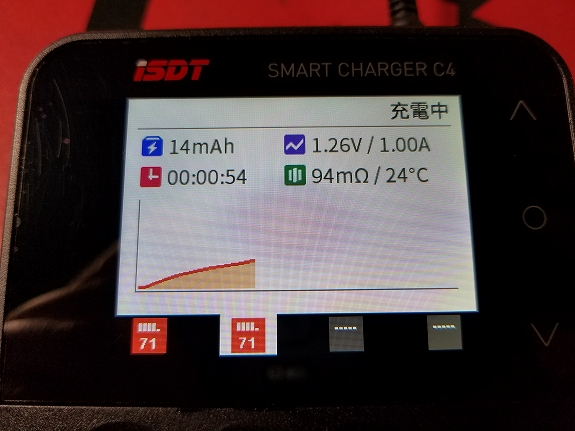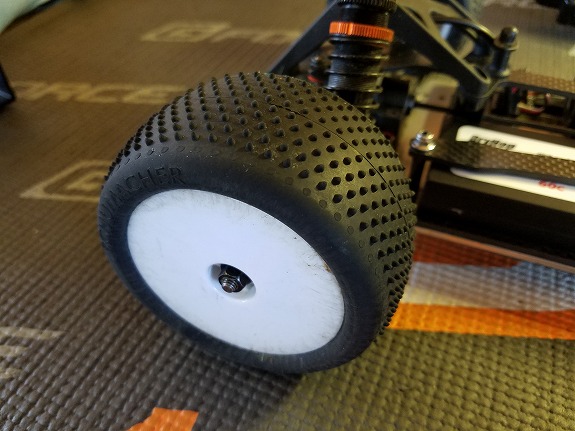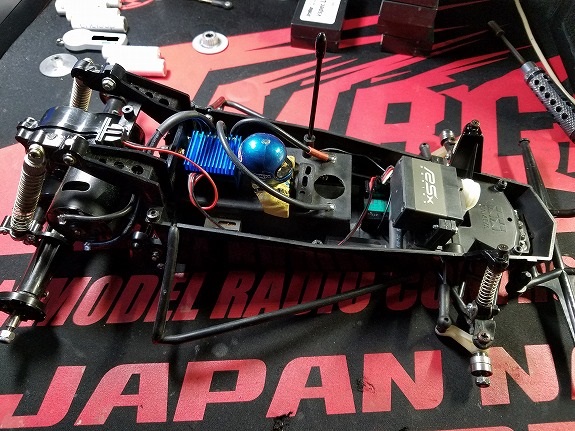ひとりごと(ブログ)カテゴリ
月別一覧
ショッピングカート
カートは空です。
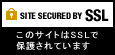
|
ホーム |
ひとりごと(ブログ)
ひとりごと(ブログ)
記事検索
ひとりごと(ブログ):2333件
HDCでテスト ③
HDCでテスト ②
HDCでテスト ①
20180723雑談
D418 ③
D418 ②
D418 ①
D418発売
20180710雑談
LP4600とLP5700HV比較
20180704雑談
ストックコンバット
20180621雑談
iSDT C4
HDCオフロードレース ラウンド65
HDC行ってきました
20180521雑談
20180514雑談
HDCサーキット
シンタニ定期レースに参戦
|