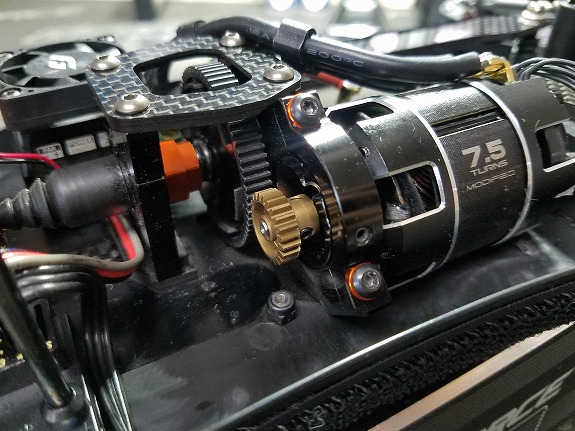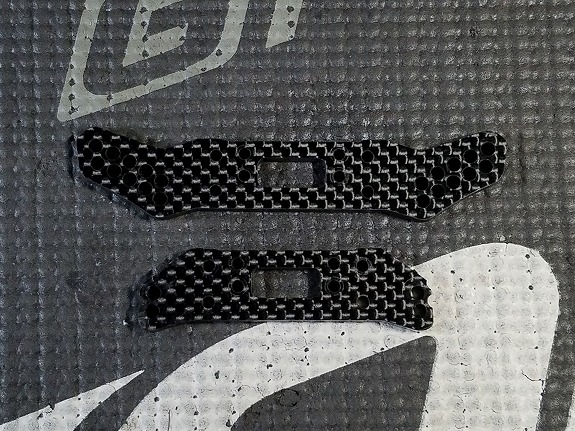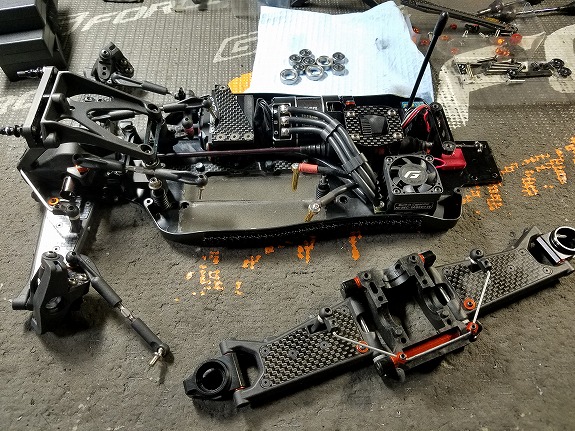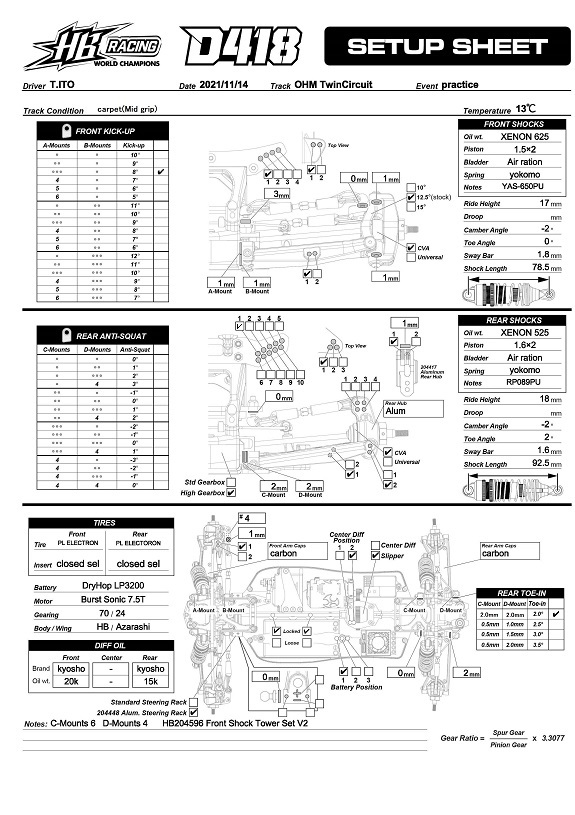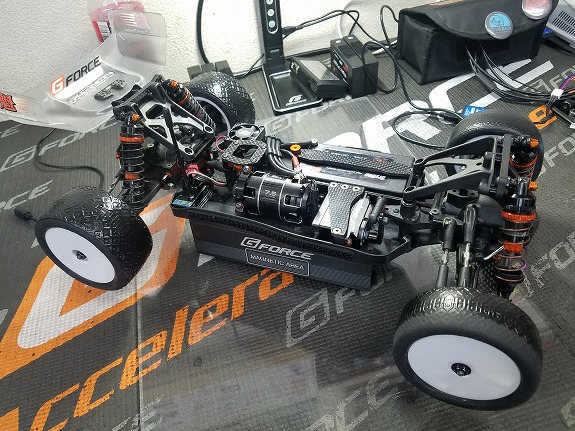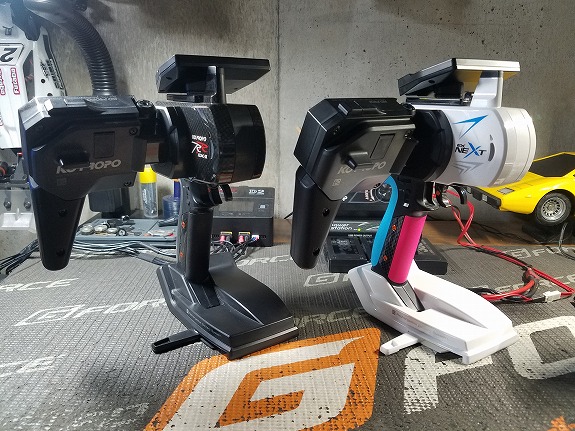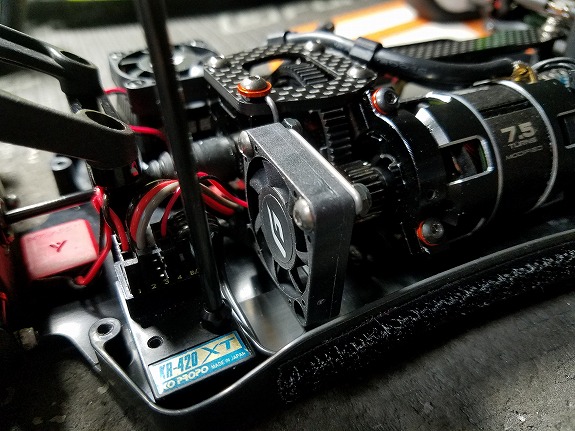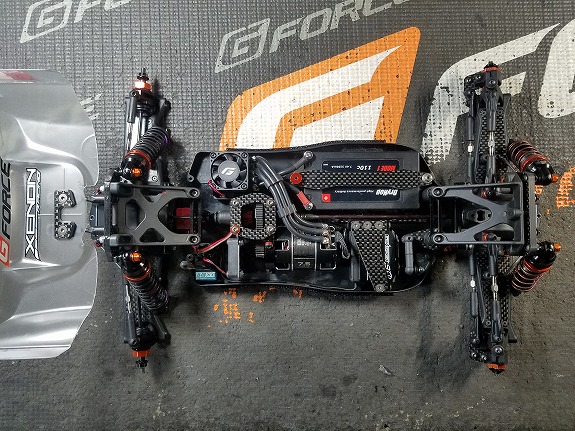ひとりごと(ブログ)カテゴリ
月別一覧
ショッピングカート
カートは空です。
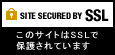
|
ホーム |
ひとりごと(ブログ)
ひとりごと(ブログ)
記事検索
ひとりごと(ブログ):2333件
トップフォースEVO
PRピニオンギヤ
ツインサーキット最終戦
BS-X4S
12月5日練習&セッティング
11月28日の練習
D318
D418
バギーチャンプ修理
シリンダー内のダンパーオイル
追記
D418メンテ
オームツインサーキットオフロードコースOPEN!
オオタキ カウンタック LP400
オームツインサーキット
STユニットスティックタイプ
D418 Fダンパーステー
オームツインサーキットオフロードコース改修開始!
D418にストックモーターを搭載する例
D418ダンパー
|